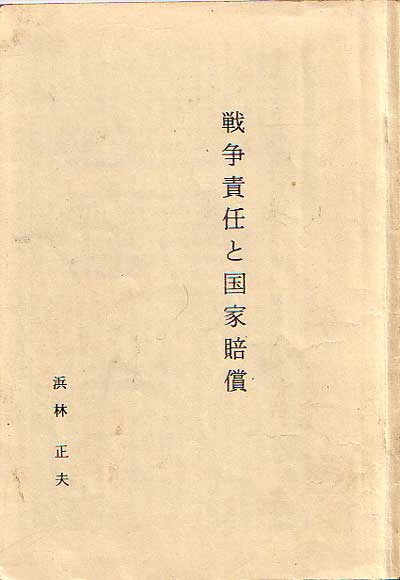

このバンフは、1998年8月16日、杉並支部第9回定期大会のとき、一橋大学名誉教授浜林正夫先生の講演を収録したものです。
なぜ戦争責任を問題にするのか、戦争責任とは何か、そのあいまい化は何故か・・など、たいへんわかりやすく述べられております。21世紀を目前に同盟運動推進、また対話をひろげる良き資料となります。ご購読と普及にご協力をおねがいします。
1999年1月 治安維持法犠牲者 国家賠償要求同盟 杉並支部
戦争が終わってもう五〇年以上たつのに、いまごろ、なぜ、戦争責任などということを問題にするのかと、疑問に思われる方も多いと思います。とくに若い方々は、自分たちの生まれる前におこなわれた戦争について、責任だとか、謝罪だとか、賠償だとかいわれても、それは自分にはまったく関係のないことだし、むしろ迷惑だという気持ちがつよいことでしょう。
しかし、これからお話ししますように、日本ではいまだに戦争責任の問題があいまいにされていて、賠償や補償の聞題もようやく最近になってから裁判で争われるようになり、いまだに決着がついていません。そしてそういうあいまいさにつけこんで、日本がやった戦争は正しかったのだとか、南京大虐殺や従軍「慰安婦」などという戦争犯罪はなかったなど、日本人の歴史認識をゆがめ、アジアの人びととの友好を傷つける発言や運動がはげしくなっています。一昨年(一九九六年)の春ごろから、中学校の社会科教科書から従軍「慰安婦」の記述を削除せよという自民党の一部と右翼が結びついた運動がおこり、また今年(一九九八年)の五月から『プライド』という東条英機を賛美する映画が東映系で上映されたことは、ご承知のとおりです。七月末に成立した小渕内閣の中川昭一農水相が就任後最初の記者会見で、「従軍『慰安婦』に強制があったかどうか分らない」、「これを教科書にのせるのは疑問だ」と発言し、あとでこれを撤回しましたけれども、やはりここにも歴史的事実をゆがめようとする意図があきらかにみられます。
このように過去の戦争責任をあいまいにしようという動きは、これまでも何回かありましたが、それはいつも憲法改悪の策動と結びつき、現在の動きも新ガイドラインや憲法調査委員会設置の動きと結びついています。逆にいえば、過去の戦争責任を明確にすることが平和憲法を守り、未来の戦争をふせぐことにつながっているのです。これが今日の私の話の結論なので、結論を先に申し上げてしまいましたが、これから本論に入ります。
戦争には必ず勝者と敗者があり、勝った方が負けた方から領土や財宝をとりあげたり、負けた方の人びとを殺したり奴隷にしたりすることは、大昔からありました。しかし近代に入るころから、戦争にもルールがあり、勝ったからといってなにをやってもよいのだということはない、という考え方がでてくるようになりました。戦争が終わったあとでは講和会議がひらかれ、講和条約が結ぱれて戦争の後始末をするようになったのです。もちろん、この場合も、勝った方が負けた方から領土や賠償金をとりたて、責任者を処罰したりするのですが、それでもそれは一応戦争当事者間の条約という形をとるようになりました。
こういう形がさらに発展したのが国際軍事裁判です。これは第二次大戦後にはじまったものですが、これはまず条約や協定によって戦争犯罪をきめておき、戦争のさいにこれに違反する行為があったかどうかを、裁判によってあきらかにし、違反があったときは処罰するというやり方です。したがって、建前としては戦争の勝ち負けに関係なく、条約・協定違反を裁くことになるのですが、しかし現実には勝者が敗者を裁くという内容になっていることは否定できません。
こういう形の国際軍事裁判は、第二次大戦後のナチス・ドイツを裁いたニュルンベルク裁判(一九四五年一一月から四六年一二月まで)と極東国際軍事裁判(東京裁判、一九四六年五月から四八年一一月まで)の二つがおもなものです。そのほかに、のちにのべますB級C級戦犯を裁いた裁判があり、現在はこういう裁判所を常設しようという動きもあります。
これらの裁判をはしめる前に、三種類の戦争犯罪がさだめられました。
(A)「平和に対する罪」。これは侵略戦争を計画し準備し開始したという罪です。
(B)「戦争法規違反の罪」。戦争法規というのは、たとえ戦争中であってもこういうことはしてはいけないという約束(条約、協定、議定書、宣言など)のことで、これはたくさんありますが、戦前のおもなものは「妻ガス等の禁止にかんする議定書」(一九二五年)、捕虜虐待禁止条約(一九二九年)などです。日本政府は養ガス禁止議定書には一九二五年に署名だけはしたのですが、どういうわけか、国会の承認はうけられず、国会がこれを承認したのはじつに署名いらい四五年もたった一九七〇年のことでした。捕虜虐待禁止条約も戦前は軍部の反対にあってこれに加入せず、加入が実現したのは一九五三年のことでした。
(C)「人道にたいする罪」。これは軍人以外の人びとにたいして非人道的な行為をおこなったものの罪です。
この三種類の戦争犯罪のうち、(B)は戦前からきめられていたものですが、(A)と(C)は一九四五年八月八日のロンドン協定できめられたものです。一九四五年八月八日というとドイツはすでに降伏しており、日本の降伏の一週間前、そして、さきにのべたように、この年の一一月からはニュルンベルク軍事裁判がはじまるのですから、正直なところ、ロンドン協定はやや泥縄的という感じもしますが、とにかく戦争犯罪というものをあらかじめきめておいて、それから裁判にかかったのでした。
A級戦犯、B級戦犯、C級戦犯というのはこの三種類の戦争犯罪のどれにあてはまるかによって、きめられたのです。
なお、最近、さきに述べたように、戦争責任をあいまいにし、歴史の事実をゆがめようとする人びとは、「東京裁判は勝者の一方的な断罪で不当なものだ」といっています。映画『プライド』もそういう考え方に立っています。そして戦後の日本人の考え方は、こういう一方的な東京小裁判の決定をそのままうけいれ、自分の国を悪者のように見ているとして、こういう歴史観を「自虐史観」とか「東京裁判史観」とかと名づけて攻撃しています。のちにのべますように、私も東京裁判が全面的に正しかったとは考えていません。しかし裁判という形をとるにせよ、とらないにせよ、戦争犯罪人の処罰ということはポツダム宣言の第一〇項にかかげられており、日本はこれをうけいれて無条件降伏をしたのですから、その処罰を不当ということは国際的な約束に反することです。なお、すでに処罰が終わってからのことですが、一九五一年のサンフランシスコ講和条約でも、その第一一条で戦争犯罪人の処罰がさだめられています。
東京裁判ではA級戦犯だけが裁かれ、BC級戦犯はアメリカ、イギリス、オーストラリア、オランダ、フランス、フィリピン、中華民国、中華人民共和国、ソ連が各地で軍事裁判をひらいて裁きました。
A級戦犯として起訴されたのは二八名で、その判決はつぎのとおりでした。
絞首刑:東条英機(首相・参謀総長) 広田弘毅(外相・首相) 土肥原賢二(在満特務機関長) 板垣征四郎(支那派遺軍総参謀長) 木村兵太郎(ビルマ派遣軍司令官) 松井石根(中支那方面軍司令官) 武藤章(陸軍省軍務局長)
終身禁固:木戸幸一(内大臣) 平沼騏一郎(首相) 賀屋興宣(蔵相) 島田繁太郎(海相) 白鳥敏夫(駐伊大使) 大島浩(駐独大使) 荒木貞夫(陸相) 星野直樹(内閣書記官長) 小磯国昭(首相) 畑俊六(支那派遣軍総司令官) 梅津美治郎(参謀総長) 南次郎(陸相) 鈴木貞一(企画院総裁) 佐薩賢了 (陸軍省軍務局長) 橋本欣五郎(陸軍大佐) 岡敬純(海軍協省軍務局長)
禁固二〇年:東郷茂徳(外相)
禁固七年:重光葵(外相)
残り三名のうち二名(松岡洋右、永野修身)は獄中で死亡し、一名(大川周明)は裁判中に精神異常となって釈放されました。
BC級戦犯として起訴された人は五七〇〇人にたっします。うち一〇一八人は無罪となって釈放されましたか、死刑判決をうけた人も九八四名におよびました。罪状の大部分は捕虜虐待の罪です。日本軍は「捕虜になるぐらいなら自殺せよ」と教えており、敵兵を捕虜としたときも、これをどうあつかうべきかを教えていませんでした。むしろ、日本刀の試し斬りと称して摘虜を殺すことを奨励したり、自慢したりする風潮がありました。こういう日本軍の人命軽視の思想が多くの摘虜虐待を生みだしたのです。
私は戦後、アメリカの文化人類学者ベネディクトの『菊と刀』という本を読んで、「日本の軍隊では捕虜になる仕方を教えていない」と彼女がおどろいているので、逆に私は、アメリカ軍では捕慮になることを教えているのかと、おどろいた記憶があります。余談ですが、終戦のすこし前の沖縄戦で多くの民間人が集団自殺をしたことはご承知のとおりですが、なかにハワイ帰りの人がいて、「武器を捨てて白旗をかかげて降伏すればアメリカ軍は殺さないはずだ」といって集団投降し、助かった人たちもいるという話をきいたことがあります。
戦争はもちろん多くの犠牲をともなう悲惨なものですが、日本軍の戦争法規についての無知と野蛮さがその悲惨さをいっそう大きくしたのです。
戦争犯罪人は個人ですが、戦争をおこなった国家もその責任を問われます。その形はさまざまですが、日本の降伏の条件をさだめたポツダム宣言では、軍国主義勢力の除去、日本の領土を本州、北海道、九州、四国および連合国のさだめる諸小島とすること(台湾、朝鮮、南サハリンを日本の頷土からとりあげること)、日本軍隊の武装解除、戦争犯罪人の処罰、実物賠償の取立てと軍需産業の禁止ということがさだめられていました。
このように戦争に負けた国から領土をとりあげたり、賠償金をとりたてたり、極端な場合には敗戦国全体を併合してしまうというようなやり方は音からおこなわれてきたことで、日本も日清戦争のときには中国(清)から台湾を奪い、二億テールという賠償金をとりたてました。これは当時の日本円にすると三億一千万円といわれ、現在の貨幣価値ではどれくらいの金額になるのか、ちょっと分りませんが、とにかくこの陪償金によって日本は金本位制をつくりあげることができたといわれていますから、かなりの巨額であったと思われます。日露戦争のときは南サハリンを奪い、中国東北部(満州)での利権を獲得するなど、いくつかの獲物を手にいれましたが、ロシア側に譲歩して賠償金をとらないことにしたため、これに不満をもった一部の人びとが「日比谷の焼打ち事件」といわれる暴動をおこしたりしました。
満州事変にはじまり第二次世界大戦にいたる戦争(これを最近は「アジア太平洋戦争」と呼ぶようになっています)をひきおこした日本にたいしても、すでにのべたように賠償の要求がつきつけられました。しかしこれは賠償金という形ではなく、実物賠償という形でした。しかもそれはいますぐ取りたてるということではなく、「実物賠償の取立てを可能ならしむるが如き産業の維持」をみとめるということ、つまり、将来、産業が復興してから賠償を取りたてるという比較的寛大なものでした。ポツダム宣言がこの点では比較的寛大であった理由は、よく分かりませんけれども、おそらく、第一次大戦後にドイツにたいして、1320億金マルクという巨額の賠償金を要求し、そのために天文学的といわれる超インフレをひきおこし、かえってドイツの復讐心をあおりたて、ナチスの台頭をゆるしてしまったという反省が、連合国側、とくにアメリカにあったように思います。
サンフランシスコ講和条約のときにも、アメリカは日本から賠償をとらないように主張しました。このころ、アメりカはすでに対日政策を転換しており、日本を反共の基地として利用するために、日本の経済復興に力を貸していたのです。しかしこれには反対する国もあり、結局、日本は賠償を希望する国と個別に交渉し、「生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の殺務」を提供するという役務賠償の形をとることになりました(そのほかに日本の在外資産の没収もありました)。実際にはアメリカだけでなく連合国の多くは賠償請求権を放棄し、日本が賠償を支払ったのはビルマ(ミャンマー)(1954年、720億円)、フィリピン(1956年、1980億円)、インドネシア(1958年、803億円)、南ベトナム(1959年、140億円)の四か国だけです。しかしこのほかに、賠償ではありませんが、それに代わる無償資金供与をおこなった国はつぎの八か国です。タイ(1955年、96億円)、ラオス(1958年、10億円)、カンポジア(1959年、15億円)、韓国(1965年、1080億円)、マレーシア(1967年、29億4千万円)、シンガポール(1967年、29億4千万円)、ミクロネシア(1969年、18億円)、モンゴル(1977年、50億円)。このほか、ビルマとインドネシアには賠償のほかに無償資金供与もおこなっており、また南ベトナムヘは賠償をしましたが、北ベトナムヘは賠償をしていませんので、1975年と76年にあわせて135億円の無償資金供与をおこないました。
これらの賠償、無償資金供与にさらに在外資産の没収などを加えますと、総計1兆362億5711万円にたっする対外支払いがおこなわれました。日本政府は、国交がまだ回復していない北朝鮮を除いて、対外支払いはすべて完了したと、1977年に発表しました。
これらの賠償や無償資金供与にはいくつかの問題があります。まず第一に、これは政府間の支払いですから、うけとった側の政府がそれをどのように使ったのか、分りません。戦争の犠牲になった人びとの役にたつように使われたとはいえないようなケースも少なくないようです。なかには、相手の国が独裁国家である場合には、せっかくの賠償が独裁者のポケットに入ってしまったケースもあるといわれています。
また日本側としても、こういう賠償や資金提供を純粋に戦争の被害への補償あるいはお詫びとしてではなく、東南アジア諸国や韓国への経済進出の足がかりにしようとしていました。したがって賠償といっても現金を払うのではなく、ダムや道路や発電所や工場などの建設という形でおこなわれ、その仕事は日本の大企業が請け負ったのです。たとえばミャンマーでは水力発電所(鹿島建設)、自動車工場(日野自動車、マツダ)、農機具工場(クボタ)、家庭電器工場(松下電器)の建設が賠償としておこなわれました。こうして賠償金はいったん相手国政府の手にわたったのちに、おそらくいくらかピンハネされて、日本企業の手にもどってきたのです。あるいはそれは形だけのことで、実際は日本政府から日本企業へ直接に支払われたのかもしれません。そしてそこには政治家も介在しました。たとえばインドネシアヘの賠償のうちには船舶10隻がふくまれていましたが、これを提供したのは木下産商という貿易会社で、この会社は当時の岸信介首相に多額の政治献金をしていました。
このように工場などの施設をっくった日本の大企業はその国へ進出する足がかりをえたことになります。賠償がそういう意図をもっておこなわれたということを、外務省もはっきりとみとめています。外務省賠償部監修の『日本の賠償』(世界ジャーナル社、一九六三年)にはつぎのようにのべられています。
「輸出困難なプラント類や、従来輸出されていなかった資本財を、賠償で供与して“なじみ”を作り、将来の進出の基盤を築くことが、わが国にとって望ましいのである。」
戦前の日本には「国家無答責の原則」といって、国はどんなことについても責任は負わないという原則があり、したがって賠償や補償はいっさいおこなわないという立場をつらぬいてきました。国家賠償という考え方がとりいれられたのは、戦後の新憲法で、その第17条にはじめて国家賠償という規定がもうけられたのです。この規定はマッカーサーがしめした憲法案にも、これをうけてつくりあげられた日本政府案にもなく、また当時各政党や個人などから提案されていた各種の憲法案にもなく、政府案を議会で審議している途中でもりこまれたものです。そしてこの憲法の規定をうけて、一九四七年に国家賠償法という法律がつくられました。
しかし戦争犠牲者に対する補償はこの法律にもとづいておこなわれているのではありません。その補償は一九五二年四月に制定された戦傷病者戦没者遺族等援護法によっておこなわれているのです。ここに日本の戦後補償のひとつの大きな特徴があります。それは戦争の犠牲になったすべての人への補償ではなく、戦傷病者と戦没者遺族、つまり旧軍人とその遺族への補償だということです。この対象はのちに未帰還者や引揚者へもひろげられましたが、基本はやはり旧軍人とその遺族なのです。
しかもこの場合、旧軍人というのは日本国籍をもつものに限られています。有名な「国籍条項」がそれです。戦後の日本のさまざまな社会保障立法(健康保険、年金、児童手当、生活保護など)にっいては、つぎつぎと国籍条項がはずされていったのですが、この旧軍人についてだけは頑として国籍条項が守られています。これが戦後補償のもうひとつの特徴です。
第三の特徴は、外国人の戦争犠牲者にたいしては、政府間の賠償はすでに完了しているので、個人にたいしては補償しないといいつづけていることです。
こういう日本政府の頑固な態度にたいして、戦後四五年もたってからですが、一九九〇年からつぎつぎと訴訟がおこされるようになりました。それは一九九八年五月現在で四一件にたっしています。訴訟をおこしているのは韓国、フィリピン、中国(ホンコンをふくむ)、オランダ、イギリス、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリアなどの元捕虜、強制連行犠牲者、従軍「慰安婦」などですが、このうちとくに問題なのは、戦時中は日本人として軍人または軍属として徴兵・徴発され、戦後は日本国籍をうしなったために補償をうけられない朝鮮や台湾の人びとです。その数は台湾人が20万7183人、朝鮮人が24万2341人、計44万9524人とされ、そのうち五万人以上が戦死しています。強制連行された人は朝鮮人が約72万人、中国人が約5万人です。これらの人びとのうち、もっとも悲惨なのは、朝鮮や台湾の出身者で日本軍人として戦争に参加し、戦後、戦犯としてとらえられ、処刑された人びとで、その数は朝鮮人戦犯148名、うち死刑23名、台湾人戦犯173名、うち26名が死刑となっています。つまり、これらの人びとは戦犯としては日本人としてあつかわれ、戦後補償については外国人として除外されてしまったのです。こういう犠牲者にたいしても日本政府はまったく心の痛みを感じないのでしょうか。
日本の裁判所はこれらの訴訟ではずっと原告敗訴の判決をくだしてきました。強制労働をさせていた企業が和解に応じて補償金を支払ったケースはありますが、国としてはいっさい責任をとろうとしていません。しかし裁判所のうちには、現在の法律では原告のいい分をみとめるわけにはいかないけれども、国としてはなんらか対応すべきだという見解をしめしたところもあり、最近になって新しい補償法を制定せよという運動が弁護士を中心にはじまってきました。
そういうなかで一九八八年に台湾人軍人の戦没者には特別立法によって弔慰金が支払われ、また、今年(一九九八年)四月、山口地裁下関支部が新しい判決をくだしました。それは釜山の元従軍「慰安婦」、元女子挺身隊員各二名が日本政府に謝罪と補償金2億8600万円の支払いをもとめていた裁判で、この訴えにたいして、元女子挺身隊員の訴えはしりぞけられましたが、元「慰安婦」にたいしては一人30万円の慰謝料の支払いを日本政府に命じたのです。30万円という金額はあまりにも少なすぎますし、また国側が控訴していますので最終的にはどうなるかわかりませんが、裁判所が、現行法では補償できないけれども、国は補償法をつくって補償すべきであるのに、それを怠ってきた「立法不作為」について国家賠償の義務があるというのが判決の理由です。こうして、外国人にたいする補償の問題にようやく少し風穴があいたのが現状です。
さきにのべましたように、日本人にたいする補償は旧軍人とその遺族にたいするものが中心です。軍人には明治以来、退官後に「恩給」という名の年金(これが日本の年金制度のはじまりです)が支給されてきましたが、終戦後、占頷軍の指令によってこれは廃止されました。しかし講和条約が締結された翌年に、さきにのべた戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定されたのを追いかけて、その翌年(一九五三年)に軍人恩給も復活したのです。この二つの制度によって、一九九四年までに約39兆円が支給され、その後も毎年2兆円近い額が支給されつづけています。一九九八年度の予算でも1兆4229億円が計上されています。日本の対外賠償・資金供与が総計1兆円余で、しかもその支払いは完了したとされているのに、国内の旧軍人・遺族には40兆円以上が支払われ、しかも今後もなおつづくというこのアンバランスのうちに、日本の戦後補償と、それを支えている歴史認識のゆがみが、はっきりとあらわれているといってよいでしょう。
軍人恩給は勤務期問(戦地加算をふくむ)が12年以上の軍人に支給され(ほかに傷病恩給もあります)、遺族には扶助料が支給されます。その金額は一律ではなく、勤務期間や現役のときの位によって大きな差があります。職業軍人を単純に戦争の犠牲者と見ることはできませんし、まして大将とか中将とか、高い位にあった人は戦争の犠牲者ではなく、むしろ推進者というべきでしょうが、そういう人びとに高い年金が支給されているということは、この制度がけっして戦争の犠牲者にたいする補償という性格のものではなく、むしろ戦争をすすめた人びとにたいする慰労金ないし弔慰金という性格のものだということをしめしています。
旧軍人以外では原爆被爆者、引揚者、徴用された人の一部、満州や沖縄で戦闘に参加させられた民間人などが補償の対象となっていますが、それらは全部ひっくるめて約1兆3千億円程度、被爆者関係を除くと数十億円にすぎません。日本の戦後補償がいかに旧軍人にかたよっているかは、この点でもあきらかです。空襲で生命や財産を失った人びとや、直接の戦災被害者ではないにせよ、戦争の準備のために犠牲となった治安維持法の犠牲者など、ほんらいの意味の戦争犠牲者への補償はまったく無視されているのです。こういう戦後補償のゆがみを正すことが、ふたたび戦争をくり返さないという平和の道につうじているのです。
ドイツの戦争犯罪もニュルンベルク国際軍事裁判で裁かれ、死刑12名、終身刑3名などの刑がくだされました。しかしドイツと日本との決定的違いは、ドイツではこのほかにドイツ人自身の手によって、9万人以上のナチス関係者がドイツの裁判所で裁判にかけられ、7千件近い有罪判決がくだされているということです。これにくらべ日本では日本人自身の手による戦争責任の追及も戦争犯罪の処罰もいっさいおこなわれませんでした。ここに日本とドイツとの歴史認識の大きな違いがあります。ついでにいっておきますと、イタリアでも逃亡しようとしたムッソリーニをとらえて処刑したのはイタリア人でした。
こういう歴史認識の違いは、戦後の補償の仕方にもあらわれています。一九九四年一月までにドイツが支払った補償額は約929億マルク、こんご支払いを予定されている額は約294億マルクで、合計約1223億マルクになります。これは日本円に換算すると1マルク80円として約10兆円となり、金額からいえば日本の四分の一以下です。しかし補償の原則は「ナチスの迫害の犠牲者にたいする補償」であって、日本のように旧軍人とその遺族に対する「援護」ではありません。それでは「ナチスの迫害の犠牲者」とは具体的には誰かというと、一九五六年に制定された連邦補償法の第一条ではそれをつぎのように定義しています。
「ナチズムの迫害の犠牲者とは、ナチズムに政治的に敵対するという理由から、もしくは人種、信仰または世界観上の理由から、ナチズムの権力措置によって迫害され、それによって生命、身体、健康、自由、所有権、財産について、もしくはその職業上、または経済上の成功にかんして、披害をうけたものである。」
もし日本でこれと同じような補償法がつくられていれば、治安維持法の犠牲者こそ真っ先に補償をうける資格があることになるでしょう。ただし、ドイツの場合にも、東西ドイツが分裂していて西ドイツでは共産党が非合法化されていたときにつくられた「共産主義者排除条項」があって、共産主義者は補償をうけることができません。この条項はドイツ統一後の現在もつづいているようです。この点ではナチスの戦争責任にたいしてきびしい態度をとり、「戦争犯罪に時効はない」としているドイツにも、やはり反共主義という限界はあるといわなけれぱなりません。
ナチスの犠牲者はドイツ人には限られず、外国人もふくまれます。ドイツの場合には政府間の国家賠償ではなく、外国人犠牲者への個人補償という形をとっており、ここにも日本の戦後補償との違いがあります。こういう形での外国への支払いは約10億マルクで、そのほかにユダヤ人への補償としてイスラエルヘ34億5千マルクが支払われ、また、ポーランドとの「和解墓金」のために5億マルクが提供されました。
一九八0年代にナチスの犠牲者の範囲は拡大され、強制不妊、断種手術の犠牲者、シンティ・ロマ(いわゆる「ジプシー」)、安楽死犠牲者、兵役忌避者、脱走兵などもふくまれるようになりました。
ドイツやイタリアにくらべて日本の場合の戦争責任の追及の仕方は弱く、そのことが国家賠償や補償にさまざまなゆがみを与えていることはあきらかです。それだけではありません。最初にものべましたけれども、過去の戦争責任追及の弱さが、現在の戦争肯定論を生みだしているのです。
戦後の日本の平和運動は戦争の悲惨さを強調することから出発しました。とくに広島・長崎の披爆体験とビキニ水爆実験の犠牲者とが、いわば日本の平和運動の原点だといってよいでしょう。それはそれとして大切なことですが、しかし、そういう悲惨さや犠牲を生みだす原因をつくったのは誰なのかということを、聞いつめる姿勢は弱かったのです。
一九六0年代から日本の平和運動は戦争の悲惨さを訴えるだけでよいのかという反省が生まれてきました。戦争の悲惨さを訴えるのは戦争の被害者の立場からのものですが、日本はアジア諸国にたいしては加害者です。このことをぬきにして、被害を訴えるだけでは平和運動としても不十分であり、歴史認識としても正しくありません。こういう反省からアジア太平洋戦争における加害の側面が重視されるようになり、一九六九年の検定に合格した高校世界史のある教科書(七一年から使用)にはじめて南京大虐殺の記述があらわれます(日本史の教科書では七四年版から)。この検定のときに、「日本の恥になるようなことを掘りだす必要はないじゃないか」という意見がだされたのにたいし、著者たちは「隠す方がかえって恥」といって抵抗したといわれています。その後、従軍「慰安婦」や七三一部隊、強制連行などの記述も教科書にとりいれられ、家永教科書訴訟にたいする一九九七年八月の最高裁判決では、七三一部隊についての記述を削除させた検定は違法であったことをみとめるにいたりました。
日本による加害の事実をみとめることはきわめて重要なことですし、みずから残虐行為をおこなったことを率直に告白している旧軍人の方々の誠実さと勇気にも頭がさがります、しかし加害責任の追及がそこでとまってしまったのでは、戦後すぐのころにいわれた「一億総ざんげ」になりかねません。個々の兵士たちを残虐行為などの極限状況へ追いこんでいったのは誰だったのかを問いつめることが重要です。私は軍隊には入りましたが戦地へはいかないうちに終戦を迎えました。もし戦地へいって敵軍とむかいあったとき、あるいは捕虜を殺せと命じられたとき、人を殺す勇気があるかどうか、あるいは命令を拒否することができるかどうか、考えていると大変不安になります。個々の兵士はたとえ善人であっても、戦地では相手を殺さなければ自分が殺されるのです。とすれば、善良な日本の青年をそういう状況に追いこんだものこそ、真の加害者なのです。
アジア太平洋戦争について語るとき、日本人は戦争の被害者であったという面と、加害者であったという面と、二つ側面をもちます。どちらの面を強調するかということで、ときに意見が対立することもありますが、私はいずれの面を強調するにせよ、国民をそういう状況に追いこんだものの戦争責任こそ追及されなければならないと思っています。
ところが、すでにのべましたように、日本では日本人自身の手による戦争責任の追及はおこなわれませんでした。戦争責任の追及は東京裁判という「外圧」によっておこなわれました。そのために現在もなお、戦争責任の問題や歴史認識の問題について、歴史の真実をゆがめようとする動きがくりかえしくりかえしあらわれるようになっているのです。
東京裁判は満州事変いらいの日本の戦争を侵略戦争と断定し、その責任者を処罰しました。ここに東京裁判の最大の意義があります。さらに戦時中、日本国民には知らされていなかった南京大虐殺などの戦争犯罪の実態をあきらかにし、その責任を追及しました。「大本営発表」ばかり聞かされていた私たちは、この裁判によってはじめて日本がどんな戦争をしていたのか、その実態を知ることができたのです。
しかし東京裁判がなにからなにまで百点満点だということはできません。そこにはいくつかの問題点がありました。
その第一は天皇の戦争責任を問わなかったことです。連合国のなかには、天皇を戦犯として処罰せよとか、少なくとも退位させよというような意見がありました。しかしアメリカは戦争中から、日本の戦後処理には天皇を利用するのが最善という判断をもち、天皇の戦争責任は追及しないと決めていたのです。
最近、東条英機を賛美する映画『プライド』が上映されましたが、そのなかで東条が弁護人の清瀬一郎と激論をかわす場面があります。それは清瀬が東条にたいし、天皇の命令に背いて戦争をはじめたといってくれと頼むと、東条は激怒して「この私が一天万乗の君のご命令に背くなどということがあろうか! そんな嘘の証言をしては死んでも死にきれん!」と反論します。東条の気持はたしかにこういうものだったと思いますが、しかし、もし東条が天皇の命令に従って戦争をはじめたと証言してしまうと、戦争責任が天皇にまでおよぶことになります。アメリカ側も日本側も天皇の戦争責任は追及しないという合意ができていたので、清瀬弁護人が必死になって東条を説得したのでした。
第二に、南京虐殺などは東京裁判でとりあげられましたが、細菌戦の研究をし、一部実行にもうつした七三一部隊はとりあげられず、その隊長であった石井四郎は戦犯にはなりませんでした。これはアメリカ軍が七三一部隊の研究成果をひきつぐための取引であったといわれています。また日本軍による毒ガス兵器の開発やアヘン栽培などの国際法逢反行為も不問に付されました。現在でも中国には100トン以上の毒ガスが遺棄されていて、日本政府にたいしてその処分が要求されているのです。
第三に、日本軍将兵による強姦などの性犯罪は重視されましたが、最近問題となっている「慰安所」という制度そのものを「人道にたいする罪」としてとらえるという視点はありませんでした。
第四に、裁判全体が侵略戦争の責任を追及するためのものであったためかもしれませんが、台湾や朝鮮にたいする植民地支配の責任は追及されませんでした。
第五に、侵略戦争の責任追及もけっして十分とはいえませんでした。このことは東条ら七名が絞首刑になった翌日(一九四八年12月24日)、岸信介、児玉誉士夫らA級戦犯容疑者19名が釈放されたことに、はっきりとあらわれています。岸信介がのちに首相になったことは周知のとおりですが、A級戦犯として修身禁錮刑になった賀屋興宣は一九五八年に出所をゆるされて、のち池田内閣の法相となり、また禁錮七年の重光葵も一九五〇年に仮出所、のち鳩山内閣の外相となりました。こういう点を考えますと、アメリカは天皇だけでなく、一部の戦犯政治家をも利用するために戦争責任追及の手をゆるめたとみることができるでしょう。
最後に、東京裁判は勝者が敗者を裁くのではなく、国際法に照らしてその違反を罰するというスタイルをとったのですが、もしそうだとすれば連合国の側がおこなった戦争犯罪もまた裁かれるべきであったということになります。連合国側の戦争犯罪として大きいのは、やはりアメリカの原爆投下とソ連によるシベリア抑留でしょう。原爆投下は一般市民をも無差別に殺傷した非人道的行為ですから「人道にたいする罪」にあたりますし、シベリア抑留は日本軍を武装解除ののち家庭に返すとしたポツダム宣言に違反するものです。しかし連合国側の戦争犯罪はまったくとりあげられませんでした。東京裁判も結局は勝者による一方的な処分に終わってしまったのです。ただし、最近になって(一九八八年)、アメリカは戦時中に収容所へ強制収容した日系人に謝罪と補償をおこないました。カナダも同様の措置をとりましたが、戦勝国がこういう措置をとるのは珍しいことです。日本がいまだに個人には補償しないという立場を固執しているのにくらべると、このアメリカとカナダの措置は、日系人の粘りづよい運動の成果であるとはいえ、やはり日本政府に反省をせまるものといえましょう。
A級戦犯容疑者が釈放されて首相となり、A級戦犯が刑期を短縮されて出所し大臣となるような日本の政治状況では、戦争責任の追及や侵略戦争への反省がおこなわれなかったのは当然といってよいかもしれません。それどころか、歴代政府首脳はアジア太平洋戦争が侵略戦争であったことを絶対にみとめようとはせず、またアジア太平洋戦争や日本の植民地支配を正当化するような政治家の発言も数えきれないぐらいあります。
ただ一度だけ、首相がアジア太平洋戦争を侵略戦争としてみとめる発言をしたことがあります。それは一九九三年八月、38年間つづいた自民党政権に代わって登場した非自民内閣の細川首相です。この発言はすぐ取消されたのですが、こういう発言がとびだしたことにおどろいた自民党は、あらためてアジア太平洋戦争(彼らはいまでも、この戦争を大東亜戦争と呼んでいます)とはどういう戦争だったのかを見直し、一九五五年に『大東亜戦争の総括』という大著を出版しました。これはたびたびくりかえされてきた侵略戦争肯定の発言を総まとめしたような内容のもので、そういう立場から見ると、現在の教科書は「偏向」しているということになりますので、これを正すためには「新たな教科書のたたかい」が必要だといっています。そのためには学者に資金を援助して教科書批判をすすめようともいわれていますが、この年のはじめに藤岡信勝東大教授らが自由主義史観研究会を発足させ、翌年、中学校の教科書から従軍慰安婦の記述を削除せよという運動がはじまったことには、こういう背景があるのです。いま藤岡氏らは「新しい歴史教科書をつくる会」を発足させ、自分たちの手で教科書をつくろうという運動をはじめています。
映画『プライド』もこういう侵略戦争肯定運動の一環として作成されたもので、製作・上映は東映映画ですが、スポンサは東日本ハウスという会社の社長の中村功という人で、この人は青年自由党という右翼政党の党首であり、「新しい歴史教科書をつくる会」の賛同者でもあります。
こういう人びとは現在の教科書に書かれている日本の近現代史の記述について、どういう点で異論をとなえているかというと、大局的な点では、明治維新いらいの日本史が侵略や弾圧などの暗黒面ばかりでえがかれていて、子どもたちに日本は悪い国だという印象を与え、祖国にたいする誇りを失わせるという異論です。そこで藤岡氏たちはこういう歴史観を「自虐史観」と呼び、日本の近代のもっと明るい面を強調しようというのです。
どんな社会にも明るい面と暗い面とがあり、現在の教科書もけっして暗い面だけをえがいているわけではありませんが、そのことよりももっと問題なのは、自分の国の過去の悪事をえがくことを「自虐」ととらえる考え方です。私たちはたとえば治安維持法をとんでもない悪法だといって批判しますが、このことはけっして自分を責めているのではなく、こういう悪法をつくった当時の支配層を批判しているのです。日本はよい国か、悪い国かなどと単純にいうことはできません。日本のなかで誰が弾圧し、誰が侵略戦争を推進し、誰がこれに抵抗したのかと見ていくことが大切で、そうすれば抵抗した人びとのなかに本当の「プライド」を見つけることもできるでしょう。弾圧した側も抵抗した側もいっしょにして、「自虐」だとか、「プラィド」だとかというのは、さきにのべた戦争責任論と同じように、本当の責任がどこにあるのかを、あいまいにしてしまうものです。
アジア太平洋戦争は侵略戦争ではなかったと主張する人びとが必ずもちだしてくるのは、あの戦争はアジア民族解放戦争だったという議論です。この議論にはいる前に、まず「侵略」とはなにかを見ておきましょう。侵略の定義については戦前の国際連盟のときから議論がくりかえされていたのですが、国際間でその定義について合意が成立したのは一九七四年国連総会の「侵略の定義にかんする決議」です(それ以前、一九三三年にソ連が「侵略の定義にかんする条約」を提案しましたが、これに応じたのはソ連周辺の六か国だけでした)。この決議によると、宣戦布告の有無にかかわりなく、他国の領土への軍事的侵入または攻撃、占領、併合、砲爆撃、港または沿岸の封鎖、他国の軍隊への攻撃などが侵略とされています。ちょっと脱線しますが、この定義によると、アメリカが最近スーダンとアフガニスタンヘミサイルをうちこんだのも侵略ということになります。さらにまた、外国に駐留している軍隊が受けいれ国との合意に反して行動した場合も侵略の定義にふくまれていますので、在日米軍が安保条約に違反して中近東まで出撃することも日本にたいする侵略になるのではないでしょうか。
余談はさておき、この定義に照らすまでもなく、満州事変いらいの(あるいはそれ以前からも)日本軍の行動が侵略であったことは明白です。国際連盟によってもそれは侵略であると断定されています。日本政府もさすがにこのことは否定できないのですが、それはあくまで侵略「行為」であって、侵略「戦争」ではないといいつづけています。中国にたいしては宣戦布告はしておらず、あれは「事変」であって「戦争」ではないというのです。ここでも戦争責任をのがれようという姿勢がうかがわれるのですが、しかし一九七二年の日中国交回復のときの共同声明では「過去において日本国が戦争をつうじて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し」と、日本政府が「事変」といいつづけているものが「戦争」であったことをみとめているのです。たしかに宣戦布告はありませんでしたが、14年間にわたって軍事攻撃と占領を続け、一千万人以上の人びとを殺害した日中間の戦争は、「事変(異常な出来事)」というようなものではなく、まさに戦争そのものでした。
アジア民族解放戦争という主張もとてもなりたつものではありません。第二次大戦が終わってアジアの国ぐにが独立したのは事実ですが、それらの国は日本に助けられて独立したのではなく、日本とたたかって独立したのです。そのことを明言しているのはべトナム民主共和国独立宣言(一九四五年九月)で、そこでは「われわれ人民はその独立をフランス人の手からではなく、日本人の手から奪いかえした」とはっきりとのべられています。中国の戦争も「抗日」戦争でした。日本は自分の領土となっていた朝鮮や台湾を解放しなかったばかりでなく、一九四三年五月の「大東亜政略指導大綱」では「マライ、スマトテ、ジャワ、ボルネオ、セレベスは帝国領土と決定し」とのべられていて、あきらかに頒土の拡大を狙っていたのでした。
映画『プライド』ではスバス・チャンドラボースという人物が登場し、この人物のインド独立運動を日本が支援したことになっています。日本がボースを支援し、ボースのひきいるインド国民軍が日本軍のインパール作戦(一九四四年、インパールはインドの東部の町)に参加したのは事実ですが、ボースはインド独立運動の主流であった国民会議派からは除名された人物で、インドをでてソ連、ナチス・ドイツと渡り歩き、日本へたどりついたという経歴の持主です。インドで独立運動をたたかっていた人びとは「日本の勝利はインドの独立を遅らせ、日本の敗北こそはインドの独立を確実な日程にのせる」と考えていたのでした。
もう一人、日本の支援をうけて独立を達成しようと考えた人がいました。それは「ビルマ(ミャンマー)独立の父」といわれるアウン・サンです。この人は現在ミャンマー民主化闘争の先頭に立ってたたかっているスーチーさんの父ですが、一九四〇年にイギリス政府の追及をのがれて日本へ亡命し、ハイナン(海南)島で日本軍の訓練をうけてビルマ独立軍を結成しました。しかし彼はやがて、日本の助けを借りてイギリスからの独立を達成することができても、それはイギリスに代わって日本の植民地になるだけのことだということに気づき、一九四四年に反ファシスト民主自由連盟を結成し、日本への抵抗を開始したのです。
日本はアジアの民族を解放しようとしたのではなく、イギリスやフランスなどに代わって、自分がアジアの盟主になろうとしていたのです。それが大東亜共栄圏といわれるものの狙いでした。
アジア太平洋戦争をアジア民族解放戦争といいくるめようというゴマカシのほかに、この戦争中におこなわれたたくさんの残虐行為をうち消してしまおうというゴマカシがあります。そのうち、代表的なものは南京大虐殺と従軍「慰安婦」です。
一九三七年12月、日本軍は南京を占領しました。将介石はその数日前に南京を脱出しましたが、市内には多くの中国兵が残っており、降伏して捕虜になったり、軍服を脱ぎすて民間人のなかにまぎれこんだりしました。日本軍はその後約二か月間にわたり、兵士・民間人、男女の区別なく皆殺し作戦をはじめ、十数万人から二〇万人ほどの中国人を虐殺しました。この事件は戦後の東京裁判であきらかにされるまで、日本国民には知らされていませんでしたが、連合国側では虐殺のはじまった直後から新聞で報道され、世界中に知れわたっていました。戦後になって日本人自身の手によってこの事件の全容をあきらかにしようという研究もはじまりましたが、同時にそんな事件はなかったという「南京大虐殺まぼろし」説もあらわれるようになりました。しかしその後、つぎつぎと新しい資料や証人があらわれ、旧陸軍将校の団体である偕行社が「まぼろし」説を支持しようとして原稿をあつめたところ、「虐殺は事実だ」という原稿もよせられ、ついに虐殺の事実をみとめ、「中国人民に深く詫びるしかない」とのべるにいたったというエピソードまであって、最近は「まぼろし」説はさすがに影をひそめたようです。もっとも、最近でも映画『プライド』のなかで、南京大虐殺の証言がとりあげられたのをきいて、東条が「わが皇軍の兵士たち」がそんなことをするはずがない、証拠もない伝聞だといって涙を流す場面があり、また熊本県議会へは、元熊本歩兵第一三連隊をはじめ当時の戦闘参加者の証言では、「虐殺というべきものについては誰一人見た者も聞いた者もなく……全く事実無根」なので、こういう証言も教科書にのせてほしいという請願もだされていますが、しかし南京大虐殺の犠牲者数については説は分れるものの、この事件の存在と、それが軍上層部の命令によるものであることについては、疑う余地はありません。とくに元ナチスの党員で、当時南京にいて難民救済の国際委員会の委員長であったジョン・ラーべという人の日記が公表され、昨年(一九九七年)、『南京の真実』という題で邦訳が出版されたことで、「まぼろし説」はトドメをさされたといってよいでしょう。
犠牲者の数については、虐殺のおこなわれた地域と期間をどう考えるか、また投降者や捕虜などの殺害を戦闘行為のうちにふくめて虐殺の犠牲者にはふくめないかどうか、などによってかなりの差がありますが、さきにのべましたように、十数万から20万ぐらいというのが、良心的な研究者のほぼ一致した数です。
従軍「慰安婦」(外国にはこれにあたる言葉はなく、「性奴隷」という言葉が使われています)についても、いろいろいわれていますが、大きくは三点、ひとつは慰安所はあったけれども、そこで働いていた女性は強制連行されたのではない、第二に慰安所は軍が経営していたのではなく、民間の業者の経営であった、第三に、当時は売春は合法的職業であり、それが本国でおこなわれたか、戦地でおこなわれたかの違いだけだ、この三点の異論をあげて、教科書の従軍「慰安婦」の記述を削除せよというのが、自由主義史観と称する人びとの運動でした。各地の地方議会へ提出された請願もそういう趣旨です。この三点はいずれも詭弁で、まず強制連行についていいますと、強制連行というのはなにも首に縄をつけて無理矢理ひっぱっていくということだけでなく、だましたり、おどしたり、さそったり、かどわかしたりするのも強制です。そのことは日本も加入していた「醜業を行わしめるにための婦女売買禁止にかんする国際条約」(一九一〇年)に明記されています。また、強制連行を指示した文書はないといいますが、そういうことを文書で指示するはずはありません(ただし警察関係の文書にまだ公開されていないものがありますから、そのなかに強制連行にかんするものがあるかもしれません)。「慰安所をつくるから女をさがしてこい」と上官に口頭で命ぜられたという兵士の証言はたくさんあります。
軍の直接経営でなく、民間の業者にやらせていたというのもデタラメで、軍が直接に経営していた慰安所もありますし、民間の業者にやらせていたとしても、それをみとめていた軍の責任はまぬかれません。「慰安婦」は商売として兵士を相手にしていたのだというのは、戦地の慰安所の実態をまったく無視するものです。本国の売春施設(いわゆる赤線)の女性はよかったというつもりはまったくありませんが、しかし戦地の慰安所はそれと同列に論じられるものではありません。いちおう料金を払うことにはなっていましたが、実際に払われだかどうかは分りませんし、いやな客を断る自由も、仕事をやめる自由もなく、一日に20人も30人もの兵士の相手をさせられ、身も心もボロボロになってしまったのです。こういう「慰安婦」を「商行為」だったなどという人には人間的な感情はひとかけらもないのではないでしょうか。しかも植民地や占領地の女性までかりあつめて「慰安婦」にしていたことは国際法上もゆるされないことです、自由主義史観研究会の人びとは、「どこの国の軍隊もやっていたことだ」とか、なかには「慰安所もない軍隊では戦争はできない」などと、極端なことをいう人もいますが、こういうものを軍としてもっていたのは日本とナチスドイツだけでした。
従軍「慰安婦」問題は国連の人権委員会でもとりあげられそのなかの差別防止・少数者保護小委員会で一九九八年八月、「慰安行為を強制した個人の刑事責任と国の陪償義務は逃れられない」という報告書が提出されました。日本政府はアジア女性基金をつくり、これで元「慰安婦」の人へ補償をしていると弁解していますが、この基金は政府からもお金はでていますが、基本的には民間の寄付によるもので、国家としての正式の賠償ではありません。そのため受けとりを拒否している人もたくさんいます。ここにも日本政府の責任逃れがあるのです。
従軍「慰安婦」についての以上の異論は完全に反駁されたのですが、教科書からその記述を削徐せよという運動はつづいています。しかもそれは、強制連行はなかったとか、軍の直接経営ではなかったとかというだけでなく(教科書にもそこまで詳しく書いたものはありません)、従軍「慰安婦」の記述を全部削除せよというのです。これは完全なスリカエです。名称はともかく、戦地に慰安所があり、そこで日本人のみでなく、朝鮮、中国、インドネシア、オランダ、マレーシア、フィリピン、タイ、台湾、ビルマ、インド、ベトナムなどの女性が日本軍兵士の性行為の相手をしていたことについては、誰も否定していないのです。その事実をまったく削除せよというのは、歴史の真実をおおいかくすことにほかなりません。
日本ではなぜ戦争責任の追及が弱いのでしょうか。これは大問題ですが、私はつぎのように考えています。
戦時中には「一億一心」とか「一億総動員」とかといわれ、戦争に負けたときには「一億総ざんげ」といわれました。みんながいっしょになって戦争をし、戦争に負けたらみんなが悪かったといって、みんなで謝罪する、こういう発想からは、誰が戦争の責任者かをあきらかにしようという考え方はでてきません。責任があきらかにならなければ補償も賠償も要求することはできません。従軍「慰安婦」や南京大虐殺の問題をとりあげると、「いまさら国の恥をさらすことはないではないか」とか、「祖父や親兄弟の悪口をいうのか」という反発がおこってきます。「国の恥をさらす」ことは、自分の恥をさらすことだから「自虐」だというわけです。
この発想では、国と国民、支配者と被支配者とがごちゃまぜになっています。国民は戦争にかりたてられた軍国主義の犠牲者なのだという視点が抜け落ちています。もちろん、国民のなかにも軍国主義に便乗して甘い汁を吸ったものもいるでしょうし、あるいは戦地で残虐行為をおかした人もいるでしょう。そういう人びとの責任は追及されるべきでしょうが、そちらにばかり目を奪われていると、もっとも重要な、侵略戦争そのものを推進した最大の戦争責任者を見失うことになります。
ところが日本ではこういう戦争責任者を追及していくと、いずれも上からの命令でやったという責任逃れがでてきます。そして上へ上へとさかのぼっていくと、最後には天皇ということになるのですが、その天皇には、すでにのべましたように、戦争責任なしとされてしまったので、結局はすべてがうやむやということになるのです。このような天皇を頂点とする無責任体制こそ、戦前の日本社会の特徴であり、そしてそれは象徴天皇制になった戦後においても心情的にはひきつがれているように思います。たとえば最近の銀行の不良債権問題にしても誰も責任をとろうとしませんし、責任追及もおこなわれていません。バブル崩壊後、不良債権の責任を問われて六千名以上が起訴され、四千名近い人が刑務所へほうりこまれたアメリカとは大違いです。
こういう日本社会のいわば体質ともいうべきものを、どう改めていくのかは難しい問題で、ここで詳しくとりあげることはできません。やはり、なにか問題がおこるたびに根気よく運動をおこしていく以外にないと思いますが、それよりもいまなぜこういうことが問題になっているのかについて、申し上げ、話を終わりたいとおもいます。
最初にも申し上げましたが、戦争責任の問題をめぐって、いまとくに教科書にたいする攻撃がはげしくなっていますが、教科書攻撃がはげしくなったのは今回が戦後三回目です。そしてそのいずれのときにも、憲法改悪と日米安保の問題が教科書攻撃の裏にあったのです。第一回目の教科書攻撃は一九五五年から五六年にかけてで、それはいまの自民党の前身のひとつである民主党が、社会科の教科書は偏向しているという内容の『うれうべき教科書』という本をだして、検定の強化を訴えたのです。それは一九五一年の安保条約の締結をうけ、鳩山内閣が憲法改悪のために小選挙区制を導入しようとしたときでした。
第二回目の教科書攻撃は一九八○年ごろで、このときは「侵略」を「進出」と書きかえさせようとしたのですか、中国をはじめアジア諸国からきびしい批判をうけ、一九八二年に文部省は「近隣のアジア諸国とのあいだの近現代史の歴史的事象の扱いには国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなされていること」といういわゆる「近隣諸国条項」を検定基準につけ加えました。このときの教科書攻撃の背景には一九七八年の、ガイドライン(日米防衛協カの指針)」と、これをうけた自民党の憲法調査会による改憲の動きがありました。
自由主義史観研究会の人びとはこの「近隣諸国条項」の撤廃を要求しています。そして、いま使われている教科書を攻撃するだけでなく、自分たちで教科書をつくろうとしているのです。このように第三回目にあたる今回の教科書攻撃は、大衆運動の形をとりいままでより以上に大規模で徹底したものとなっています。その背景には一九九七年の「新ガイドライン」と憲法調査委員会を国会内に常設しようという動きとがあることはあきらかです。
| 著者 | 書名 | 出版社 |
|---|---|---|
| 洞富雄、藤原彰、本田勝一編 | 『南京大虐殺の現場へ』 | 朝日新聞社 一九八八年 |
| 粟屋憲太郎、田中宏、三島憲一、広渡清吾、望田幸男、山口定 | 『戦争責任・戦後責任-日本とドイツはどう違うか』 | 朝日新聞社 一九九四年 |
| 小田部雄次、林博史、山田朗 | 『キーワード 日本の戦争犯罪』 | 雄山閣 一九九五年 |
| 吉見義明、川田文子 | 『「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実』 | 大月書店 一九九七年 |
| 俵義文 | 『教科書攻撃の深層』 | 学習の友社 一九九七年 |
| 笠原十九司 | 『南京事件』 | 岩波新書 一九九八年 |
| 「教科書に真実と自由を」連絡会編 | 『いまなぜ戦争責任を問題にするのか』 | 教育史料出版会 一九九八年 |